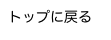現在行っている研究、これから進める研究
ここでは、現在進行中の種分化と適応の機構に関係する研究について簡単に説明します。
未発表の内容ですので簡潔になります。
これまでの研究のページで説明した、視覚の適応が引き起こしてきた種分化の機構の研究の始まりはオプシン遺伝子が種分化に関与してきたことを見出したことでした。これはシクリッドの種間が極めて遺伝的に近縁だということを利用して、多くの候補遺伝子の解析から見出したことでした。
この研究では候補遺伝子の解析の代わりに、ゲノム全体から種分化や種特異的な適応に関与したゲノム領域とそこに含まれる遺伝子を明らかにしようとしています。現在までに多くのこのようなゲノム領域が存在することが明らかになってきています。これらの領域に含まれる遺伝子の機能と適応や種分化における役割を明らかにすることにより、さらに種分化の機構が解明されると期待できる研究です。


シクリッドの種分化や種特異的な適応に関するゲノム領域の特定


インドネシア、スラウェシ島固有のマカクの種分化や種特異的な適応の研究
スラウェシ島に調査に行きました。これからエキソーム解析などで候補の遺伝子を絞り込み、その解析を行って行きます。霊長類研究所の今井啓雄先生との共同研究です。

南極の海の氷の下の世界での視覚の適応
南極大陸の周囲には厚く氷が張り出しており、その下に届く光は厚い氷のフィルターを通ってきているので、光の成分が浅瀬の海とは大きく異なっています。このような環境に生息する魚は視覚を生息環境の光に適応させているのではないか?、という疑問からこの研究が始まりました。現在、氷の下の魚のオプシンの配列を決めており、氷の下の視覚の適応が徐々に明らかになってきています。この研究は総研大の大田竜也先生と永田君との共同研究で行っています。

キューバのアノールの視覚の適応の研究
カリブ海の島々には数多くのアノールトカゲの仲間が生息しており、様々な環境に多様な適応を遂げています。この研究ではのキューバに生息するアノールについて、視覚の適応を明らかにしようとしています。研究に用いている種はそれぞれ異なった光環境に生息しており、視覚の適応が期待されます。現在、オプシンの配列をそれぞれの種で決めているところです。この研究は東北大学の河田雅圭先生との共同研究で行っています。
南極観測船「しらせ」。横須賀の港に停泊していました。


卵生メダカの視覚の適応と種分化
卵生のメダカの仲間にはオスの婚姻色が種ごとに多様化しており、種ばかりではなく集団間でも異なっている種がいます。このような婚姻色の多様化は、光を受容する視覚の多様化の結果生じたと予想されます。このような卵生メダカの視覚の多様化を調べるため、始めにオプシン遺伝子の配列を調べています。

メス化をさせるB染色体のメス化の機構解明とゲノム配列の決定
シクリッドの1種では、B染色体を持つとメス化します。B染色体とは常染色体や性染色体とは異なり、集団中の個体ごとに保有する数に違いがあり、それがなくても生存には関わりのない染色体です。この特殊なメス化させるB染色体は、どのようにメス化を起こしているのか?その機構を現在明らかにしつつあります。これまでに推定したB染色体のゲノム配列から、メス化を起こす原因遺伝子を予想しており、本当にその遺伝子が原因でメス化が起きているのかを実験で証明しようとしています。それとともに推定したゲノム配列が本当にB染色体由来であるか、B染色体のゲノム配列を直接決めて確認しようとしています。B染色体のゲノム配列は総研大の田辺秀之先生と共同で決めようとしています。




タンガニイカ湖のシクリッドの深場での色覚の適応
タンガニイカ湖にはこの湖の固有種が約250種生息しています。その中でも水深100m近くに生息する種類は、特殊な光環境に適応していると予想され、実際に暗いところで働くRH1では視覚の適応が見られています。現在、現地で収集した眼のRNAサンプルを用いて、色覚の光環境への適応を明らかにしようとしています。



サンゴの適応
進行中の研究であまり詳しく説明できませんが、サンゴの適応について研究しています。